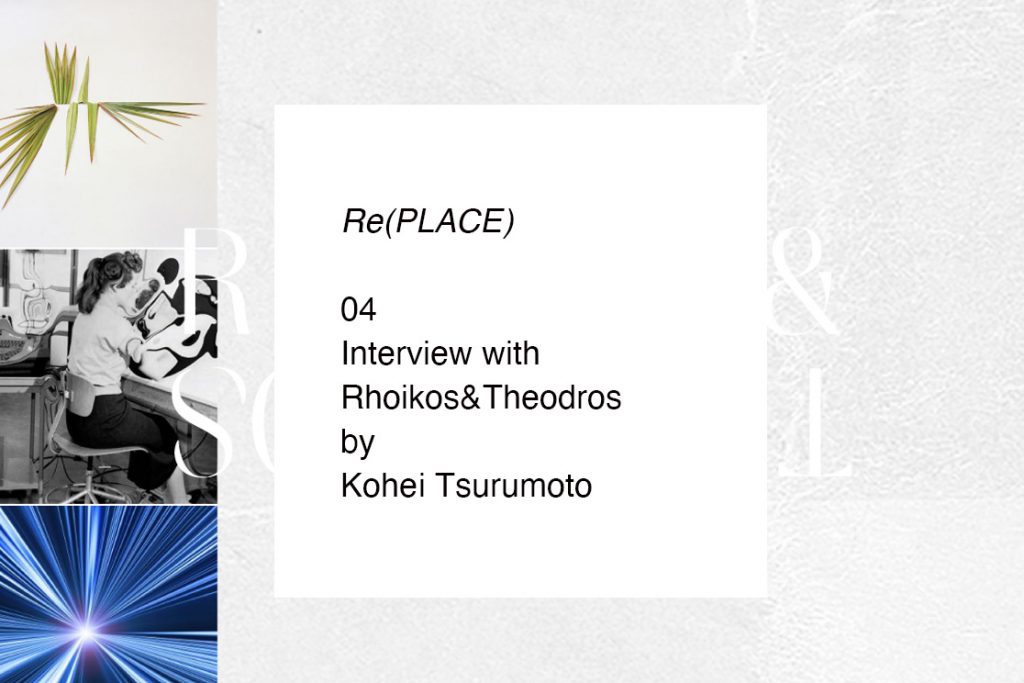Re(PLACE)03 | 白色に相当する何十もの言葉を知れば、単色の北極圏も多彩に感じることができる
text by Arata Sasaki
20代の中頃から毎朝、本を7冊並行して読むようになった。小説、詩集、批評、エッセイ、学術書 (ときどき漫画) などジャンルも形態も異なる本をそれぞれ10ページずつ読む。友人からは変わった読み方だね、と揶揄われることもあるし、それぞれの領域に屹立する歴史的な作品を順に読んだ方が体系的な学びに繋がることもわかっているのだが、個人的には本来交わらない領域が重なっていく読み方が好きだ。露悪的に言えば衒学的でとりとめもない散発的な読み方な訳だけれども、おそらく自身の飽き性を誤魔化す為にぼくの脳が仕方なく編み出した手法なのだろう。
それでも長く続けていくと、マージナルな有用性を帯び始めてくる。それぞれの世界の異なるルール、文体、言語体系の境界が朧げに立ち顕れて見えてくる景色が変わっていく。自分の見ている世界が相対化され、新しい世界の視点を手に入れたような感覚を得るのだ。そうした感覚は本に限ったことではなく、普段自分が触れえない領域に生きる人、言語体系が異なる人と交わる時にも感じることだ。たとえば育ってきた文化圏が違う異国の人たちと会話したりして、彼らの視点や文化に触れた瞬間がその最たる例だろう。
そのようなことを感覚的にずっと大切にしてきたが、数年前に『文化人類学と言語学』という本に出会って妙に納得することになった。その本に書かれている「サピア=ウォーフ仮説」に拠れば、言語の構造がひとの認知に直接的な影響を持つという。異なった言語を知ることは、異なった世界の見え方を会得する可能性が極めて高いというのだ。例えば、氷雪地帯に住むイヌイットは、白色に相当する何十もの「言葉(TEXT)」を持つので、単色の北極圏世界をぼくたちよりも多彩に感じている可能性があるという。
この仮説は何も異国の言語に限ったことではないだろう。同一言語であったとしても、別の文脈を持った言語体系であれば、あらたな認知能力の獲得がなされる。同じ「もの」や「こと」、空間や現象を見ても異なる言語体系にふれれば、全くあたらしい世界として見ることができる。このHITSPAERというキュレーションサイトを始めたのも、未知のビジュアルや体験を言語化して自分の血肉として内に取り込むことが契機だったし、きっとぼくが興味があるのは、そのような他者の視点に触れて、一時的にでも視点を交換し、世界をあらためるということなのだと思う。だからぼくは「もの」や「こと」を生み出す人間をつぶさに観察して、可能な限り言語化を試みたいと思っている。無意識から意識の領域にその姿を露わにさせることこそ人間の進歩の一つなのだから。

「Rhoikos&Theodoros(ロイコスアンドテオドロス)」の武藤 亨氏と小宮山 洋氏に最初出会った時、ぼくが感じたのは、まさに初めての人種にふれた感覚だった。もちろん同じ日本語を使用するのだけれども、同じ言葉でも文脈や使用方法によって意味が異なってくる。そのような意味において、彼らと言葉を交わした時、異なる言語体系に生きる人に触れたような特別な感触を抱いたのだ。そして、同時に重なる部分もあり、親近感のようなものも抱いた。会社に属さず個人でオルタナティブに戦っていたり、あるいは単純に年齢の近さや似かよった青年期の歩み方もあって同志のような感覚を覚えたのかもしれない。
非常に個人的なことだけれども、彼らに会ったのはぼくが30代に入ってからであり、その周期はちょうど多くの知り合いを闇雲に作るフェーズから、根底でシンパシーを感じる人々と親交を深めていく時期だった。それ以前──20代前半から中頃にかけては──とにかく知り合いを増やし、傷付けあいながらも自分自身が何者かを知らなければいけないという、人間関係における彷徨時代だったから、随分つまらないことで敵愾心を抱いたり、嫉妬したりして、その当然の帰結として少なくない数の人が周りから離れていった。彼らに会ったのは、そうした周期が終わり、ちょうどあらたな人間関係が形成され始めた頃だった。
そのような意味で、彼らとは少し落ち着いた友人関係として始まったと言えるかもしれない。互いに極度に依存することもなく、一年に数回会ってそれぞれの現在地を確認する。そして、たまに仕事も一緒にするようなプライベートとパブリックのあわいが溶け合うような関係である。だからこそ、「Rhoikos&Theodoros」として新しく活動を始めた彼らから、寄稿文を書いて欲しいという依頼がきた時、正直悩むことになった。個人的には非常に嬉しい申し出だが、近しい人たちの活動ほど批評が難しい場合がある。どうしてもバイアスがかかり客観性が失われてしまうし、彼らが主に活動しているファッションやプロダクトデザインの領域からぼく以上の適任者がいるかもしれない。それぞれの業界内から詳しく紐解いて、今回の展示について鋭く批評を投げかける、そんな人がいるのではないかと考えたのだ。しかし、その一方でそうした懸念を打ち消すくらいぼくは彼らの活動に興味を抱いていたし、言語化することでぼく自身もあらたな世界を見渡す視座を得られるかもしれないと思った。役不足かもしれないが、彼らの活動をまだ知らぬ人々に「言葉(TEXT)」にして伝えたい、という想いもあった。
結局のところ悩んだのは数時間のことで、こうして「書く」ということを決めた訳だが、予想していた通り数日間は何を書くのかぽっかり宙に浮いたままだった。正直に言えば ( PLACE ) by method での展示がスタートして、ますますその答えは霧の中へと潜っていった。ぼくよりも彼らの領域を専門にしている人は大勢いるから、解像度や精度で面白い記事が書けるはずがない、という強迫観念に近い想いはますます強くなっていったのである。様々なアイデアが浮かんでは消えていく中で、ぼくが書けることは彼らのパーソナリティなり、アイデンティティなり、つまりその人らしさという人格から生み出された独創性や哲学、思考を友人として普段垣間見ているからこそ見えてくるもの、そこに光を照射することで、「Rhoikos&Theodoros」の示したいことを朧げに輪郭だけでも顕にできないかと考えた。これならぼくなりの進入角度で、彼らの今後の活動を測る上でのひとつの道標を読者の方々に提示できるかもしれないと。だから、本稿では彼らとの出会いからその後の親交までを通じて、ふたりそれぞれのパーソナリティ/アイデンティティを読み解き、「Rhoikos&Theodoros」へと繋がる、「言葉(TEXT)」の拡張を試みたいと思う。この言語化によってあなたの普段見ている世界が少しでも多彩に感じられたら嬉しい。

<空>を想起させる余白の空間
相対的関係性を重んじて現れたアイデンティティ
『Jens (イェンス)』のディレクター武藤 亨氏に初めて会ったのは、Preview と題されたコレクションがまだ2、3回しか行われていない2016年くらいだった記憶がある。共通の友人を介してぼくたち三人は食事をした。
事前に Jens のコレクションイメージを見ていたぼくは、正直なところ、彼のパーソナリティや嗜好性に意外な第一印象を抱いたことを覚えている。Jens は、プロダクトやインテリア、アートなど空間を演出するものも身につけるものと同軸に捉えて提案するレーベルだが、誤解を恐れず言えば、Jens のファンになる人はどこか俗世に溢れる雑多なものとは距離を置き、コンテンポラリで洗練された暮らしをおくっている女性というような印象だった。当然、Jens を生み出した彼もそのような暮らしを好んでおくっていると思っていた。
しかし、初めて会った彼は、洗練された都会的なイメージに相反するとまでは言わないが古い居酒屋やアンダーグランドなカルチャーも好きというような妙に人間くさい一面を持っていた。あるいは、彼の幼少期や学生時代の話を聴いたせいだろうか。兎にも角にも、ぼくが勝手にイメージしていた人物像とはかけ離れた印象だった。
不思議なことに、その時の印象はその夜から少しずつ溶けていくことになる。例えば、18SSの蔦サロンでの Preview では、Jensのコレクションが、日本の古き良き時代の内装、襖や絨毯などと不思議な調和を見せた展示空間だった。個人的にはこのシーズンのコレクションこそ、武藤 亨という、ある種の複雑性を持った人間性をそこはかとなく現していたように思う。繊細さと大胆さ、古さと新しさ、男性性と女性性、匿名性と記名性。その展示からは彼の内にあるアンビバレントなものがちらりちらりと垣間見れるようだった。
初めての出会いからいつの間にか、年に二、三度くらいのペースで彼の家に行き、彼の奥さんも交えて一緒に食事をするようになった。その人間を知りたければ自宅に行け、と誰かに言われたことがあるが、そうした機会を得たことで確かに彼らしさを知ることができたような気がする。そんなエピソードをいくつか紹介したい。
ひとつは制作過程における大切なインスピレーションとして、リファレンスとなるものを熱心に収集している姿だ。ぼくと彼の奥さんが料理をしている合間に、彼が熱心にPCを操作しているを見てその過程を覗かせてもらった。そこには、コレクションのコンセプトを固めるためのイメージや資料が大量に集められていた。しかも、服やジュエリーの造形というコレクションに直接関係するものよりも、絵だったり、美術だったり、建築物だったり、一見無関係に見えるものだ。無意識下にあるものも含めて彼の感性の網に引っかかるものをひたすらリファレンスとしてアーカイブしているのが印象的だった。
もうひとつ彼らしいと思ったエピソードがある。数人でジェンガをしようとなった時、彼はゲームには参加せずに見守るポジションに率先してまわった。その行為は、その空間で誰がどのように振る舞うのかを俯瞰して観察するような、プレイヤーではなく第三者的な視点に立ちたがる、表舞台から一歩引いて全体を眺めているような姿勢にぼくには映った。そのせいかわからないが、彼からはいつも部屋の天井あたりから見ているような視点を感じる。何が起こっても自制心を失わず冷静な姿で振る舞う。このパーソナリティは彼が単純にデザイナーというプレイヤーだけでなく、空間やプロジェクト全体に向けられた包括的な視点を持ったディレクターを兼任していることに繋がっているかもしれない。
また、彼のパーソナリティ/アイデンティティを探る上での重要な要素として、『Jens (イェンス)』というレーベル名を挙げておきたい。最初この名を聴いた時、そこに重要なメッセージが込められているのではないかとぼくは思っていた。彼らしさ、彼の独創性に対する哲学が顕現されているはずだ、と。ぼくの予想に反して彼の答えはあっさりしたものだった。「ドイツ語圏内で男の子によく使われる名前をつけた。特別なメッセージは込められていない」。彼からこのことを聞いた時は多少驚いた。”名は体を表す”ではないが、名そのものに彼の核となるものが現れ出ているのではないか、と期待したぼくは肩透かしを喰らったような心持ちになったことをよく覚えている。
しかし、それから数年の歳月が経過し、その間に Preview 並びに「BLUE」「BLUES OPENING」「SPACE CURATION」など様々なプロジェクトが催されるのを見て、その名がぼくの中でもしっくり馴染んでいくようになった。アイデンティティへの概念は過去から現代に向けてアップデートされ続けており、その社会的認知に呼応するかのように Jens という名の概念もぼくの中でアップデートを遂げていた。つまり、一世紀前のアイデンティティの概念というものは固定されたもの、どのような状況や環境でも揺るがないと信じられてきたが、現代に至っては時と場合、環境によってアイデンティティは水の状態変化のように絶えず変わり続けるものであり、多様な側面が存在すると認知されるようになってきたこととクロスオーバーする。
なるほど、確かに『Jens (イェンス)』という名には固有の揺るぎない特別な意味は付与されていないかもしれないが、各々のプロジェクトを拾い集めて丁寧に繋げていくと、ぼんやりとその輪郭が露わになっていくようだ。名そのものに特別な意味を持たせず、言わば中心にぽっかり余白を作ることで周囲のそれぞれの側面に現れる境界線が際立ってくる。まるで<空>を想起させるような余白の空間だ。そのような意味では、Jens の活動を形で現すならば、周りとの相対性が顕現しやすい「円, CIRCLE」あるいは「球体, sphere」のようなのものがぼくの頭の中にはぽっかり浮かんでくる。つまりそれはトップダウンのようにアイデンティティを他者に植え付けて理解してもらうというよりも、他者による相対的関係性の中で現れる多様な側面を観る側が自由に解釈していくという形と言えるのではないだろうか。
デザイナーの名を冠とする、強烈な自我が周りを巻き込んでいく西欧型のブランドの在り方ではなく、それぞれの関係性の中から鏡のようにアイデンティティを周囲から写し出してもらう姿勢が「Jens」の、いや、彼の根底にはあるような気がするのだ。

現在の自分を形成する台座なるもの
モノになる前の形を想い描く
プロダクトデザイナー 小宮山 洋氏に初めて会ったのは、おそらく8、9年くらい前に、これもまた武藤 亨氏を紹介してくれた共通の友人を介してだった。その当時、彼は大学時代の友人と共にデザインユニットを組んでいて、それぞれの名を連ねたチャーミングなユニット名が印象的だった。その出会いからぼくたちはいつの間にか自然に仲良くなって、食事に行ったり、一緒に仕事をするようになった。ある企画で彼のご両親にインタビューさせてもらったり、ぼくの東京出張の際には自宅に泊めてくれたり、気づけば本人だけでなく家族の皆さんにもお世話になっている。
そんな彼のパーソナリティを探ってみると、これがまたなかなか掴みきれない。似たタイプが思いつかないほど独特の個性を放っている。最初に会った時に衝撃を受けた、その独創的なヘアスタイルは見慣れたものの、多くのことが謎に包まれていて、会うたびに新鮮な驚きをぼくに与えてくれる、まさに言語体系が異なる人だ。ただ人間や物事に対する好奇心が強く、且つ、柔らかいコミュニケーション能力を持つので、異なる意見を持った人でも衝突するのではなくまず調和を図るというイメージは出会った頃から今でも変わらない。
彼のデザイナーとしての個性をあらわすプロジェクトとして、金型作家 室島 満氏と共に行っているリサーチプロジェクト”mold”の一環として展開されてきたプロダクト/オブジェ「Gravity」を挙げてみたい。このひとつひとつが歪な形態のプロダクト/オブジェはぼくの小説個展の際に借り受けたのだが、そのコンセプトから彼のデザイナーとしてのステートメントが垣間見れるような気がする。
「Gravity」は射出成型によってできた同じ形状のアクリル樹脂製のボトルを、熱を持った状態のまま天井から地面に「落とす」ことで偶発的なカタチが生まれる。大量生産のプロセスに自然現象を一つ加えることで、たった一つだけのモノを量産することをテーマにしているという。ここには大量生産とたったひとつだけのモノという相反するものの融合、換言すれば大量生産というシステムの中に作家性を忍ばせるという戦略的な意欲が感じられる。
研究をベースにしたそのプロジェクトを知ってからまた少しずつ彼への見方が変わり始めて、それから随分その人となりを捉えようと観察してきたつもりなのだが、知れば知るほど余計に捉えどころがなくなっていくような気がしている。ある側面を覗いて納得した途端、あらたなに事実が掘り出されて未だにそれは更新され続けているのだ。なかなかそのような人は周囲でも稀有で分析が難しいのだが、そんな中でもパーソナリティ/アイデンティティを探る上で重要だと思われるエピソードを挙げていきたい。
一つは共通の友人とともにレンタカーを借りて、三人で埼玉県立近代美術館で開催された「竹岡雄二 台座から空間へ」展を見に行った時のことだ。展示自体をディスカッションしたことも大きいけれども、ふいに彼自身の意外な側面を知ったのは車中でのたわいもない会話からだった。おそらくぼくたちは車中で少しだけナイーブに、ちょっとだけハイになっていたのだろう。夏の終わりで、幼かった頃に謳歌した夏休みなるイベントへのノスタルジアが車中には溢れていたせいかもしれない。展示の「台座」というテーマをきっかけに、ぼくたちは現在の自身を形成する [台座]、つまりアイデンティティの確立までにどのような「もの」や「こと」に影響されてきたのかをそれぞれ吐露しあった。
車内には10代から20代頃に聴いていた懐かしいHIPHOPが流れていて、彼は仕事をし始めた頃の話をしてくれた。精神的にも肉体的にも疲弊して家でひたすら音楽を dig していた時期があった、と彼はそう述べた。小宮山 洋とはどのような人間なのかと問われたら、ぼくはまず真っ先にこのエピソードと背景で流れていた音楽を思い起こすだろう。その曲たちは確かに彼を Represent するもの、つまり「台座」の一部になったのだと。特に今回の「Rhoikos&Theodoros」の展示では、リファレンスという作り手にとっては切って切り離せない要素を公開しているだけに、参考/参照/文脈を重んじるHIPHOPと彼の繋がりがぼくの脳内にぱっと浮かび上がってきた。まさに過去に話した会話の点が現在の点と結びついたような感覚だった。
もう一つは彼が幼少期に描いた自画像を観たことだ。きっかけは彼のインスタグラムで、ドローイングがアップロードされ始めたことだった。彼はユニットやチームをさまざまな場所で築いているので、人によっては全く印象が異なるかもしれないが、ぼくの場合の出会いはプロダクトデザイナーとしての彼だったので、そのドローイングの画力には驚かされた。もちろんデザイナーと名乗るのであれば絵が上手くても何ら不思議ではないのだが、そのドローイングは単なる素描という域を遥かに越えたクオリティだった。
彼のドローイングを誤解を恐れずに言及するとしたら、モノになる以前の要素に着目して描く(既成概念である形の拘束から逃れるために、そのもの自体を概念的に一度溶かして再構築する)、とでも言えようか。すべてのドローイングがそのような描き方をされている訳ではないが、単なる模写ではなく、質の良いインスピレーションを誘発する為にあえて抽象性を重んじたドローイングが多い印象がある。頭の中にあるまだ言葉すら付けることができない小さなイマジネーションを絵に落とし込んでいったら、偶然描いた線が新しいプロダクトやオブジェのある一部へと変異/成長を遂げたというような。これはぼくの想像であり直接聴いた訳ではないのだが、文学の世界のオートマティスムのような、あたかも何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に手を動かしていたからこそ生まれたドローイングという印象が強い。そして、そのアイデアから少しずつ理性を働かせて、実際のプロダクトへと肉付けしていくような印象だ。
こうして彼のドローイング作品へのアプローチにぼくは密かに興味を抱いていたのだが、昨年、とあるプロジェクトで彼の両親に「家族」をテーマにしたインタビューをさせてもらう機会を得た。彼の確かなアイデンティティが形成される以前を知る両親に会ったことは、当然のことながら彼独特の世界観を読み解く上では貴重な体験だった。
彼は小さな頃からよく絵を描いていて、それを証明するかのようなポートレイトが実家には飾られていた。その絵は自身を鏡に映してじっと観察しながら完成させた作品で、絵に対する自信に繋がった契機になったものだったという。そこには、小学生らしからぬ技術力のみならず、素晴らしい作品がすべからく共通して持つ、ダイナミックな霊感のようなものが潜んでいた。絵には天から与えられた先天的な直感力と、後天的な努力によって生まれた粘り強い観察力の賜物が浮かび上がっていて、ようやくぼくは彼の感性とアイデンティティの根をつかまえたような心持ちがした。
それでもぼくは彼に会うと、目の前にいる本人と作品がうまく結びつかないような不思議な感覚に揺さぶられる。幼少期を過ごした空間を少し体感したからといって、彼のルーツとなる一枚の絵を見たからといって、そうそう簡単には実体を掴ませない、複雑なパーソナリティや感性がどうやらまだ眠っているようだ。だからこそ彼は多様な人や「もの」や「こと」に強い好奇心を持ち、ユニットやチームを結成して、眠っている自己を他者を通じて発見しようとしているのかもしれない。少なくともぼくの目にはそのように映っている。

そして、「Rhoikos&Theodoros」へ
ぼくは「Rhoikos&Theodoros」のふたりとそれぞれ別々に主にプライベートで親交を深め、彼らのパーソナリティ/アイデンティティを通じて、作り手としての手法や哲学にふれてきた。そこにはぼくが日常的に使用しない「言葉(TEXT)」やクリエーション作法が使用され、最終的なアウトプットへ落とし込まれている。そしてぼくは最終的な作品には、必ず作り手のパーソナリティ/アイデンティティが顕現されるものだと思っている。それがどのくらい薄められていても、本人たちが隠そうとしても、その痕跡はどこかに感じられる筈だと。寧ろ、その「らしさ」がなければ、他者を魅了できないとさえ考えている。
そんなぼくが彼らの初個展の作品を見て感じたことは、ふたりのパーソナリティ/アイデンティティが互いに押し引きをはかりながら、重なったり、離れたりして、絶妙な形で最終的には調和していった痕跡が見えたことだった。これは彼らが共通して持つ、コラボレーションをしたり、ユニットを組んだり、つまり他者を通じて自己=作品に向き合い創出していく過程を好むという、調和型の人間というパーソナリティが功を奏したのだろうと思う。たとえば、他の組織、個人の活動を作品に取り込むことで生じる関係性や空間、モノに拡張、新たな意味や体験の創出は、Jens のクリエーション手法がそのままベースになっているし、作品それぞれの造形には、形の拘束から逃れる、モノになる以前の要素に着目されており、これは小宮山氏のプロダクトやドローイングに垣間見える着眼点に近いと思う。「もの」「こと」を生み出す時にレファレンスを重んじるという姿勢はそれぞれのパーソナリティを読み解くエピソードで挙げた通り綺麗に重なる部分であり、これが「Rhoikos&Theodoros」の創造性における台座となるものだと感じた。おそらくそれぞれのパーソナリティ/アイデンティティを重んじながらディスカッションしていったら、自然に重なりと異なる部分が明瞭となり、程よい調和とそれによって生まれる拡張へと向かったのではないだろうか。
そしてこのことを換言すれば、今回の「Rhoikos&Theodoros」は、それぞれ個々のパーソナリティ/アイデンティティの延長にあるものだが、決して一人ではこのような形として帰着しなかった、とも言えるだろう。彼らがユニットとして組むことにしたのは、やはり、他者から認知された社会的な (ある程度固形化された) アイデンティティから離れて、もう一つ (彼らの数多くあるパーソナリティの中の一つと言った方が精確かもしれない) の人格が自由に振る舞える、且つ、ひとりではなし得ない自由な実験場を設けたかったからこそ為し遂げられたものだと思う。
こうしたふたりのパーソナリティ/アイデンティティに鑑みると、このユニットの結びつきは必然的であるとすら思えてくる。弱い部分は補い合い、持ち味は重なり合うことで強度を増して拡張していく。そのバランスが絶妙でどちらかの要素が強いと感じることもなく調和している。
なるほど、そのようなふたりのパーソナリティ/アイデンティティを読み解いていくと、ぼくが彼らの展示を実際見てどこか気恥ずかしいと思った感覚は、よく知る友人同士の新婚生活を覗いてきたような、くすぐったい感覚に似ているせいか。初個展の01の作品には「Moving 引越し」と名付けられているので、展示会場である ( PLACE ) by method を彼らの新居と見立ててみると、「Speaker スピーカー」、「Curtain カーテン」、「Closet クローゼット」、「Telescope 望遠鏡」など、「Rhoikos」と「Theodoros」の新婚生活のための新居 (あるいは自由にインスピレーションや創造力を引き出す為の空想上のふたりのスタジオ) に置かれたインテリア/プロダクトにさえ見えてくる。
もちろん、彼らは普段別々にスタジオを構えて働いているし、家に帰れば家族と豊かな時間を過ごす筈だ。しかし、彼らの内から生まれた新たなパーソナリティの一部である「Rhoikos」と「Theodoros」は、またこっそり家を抜け出して新しい実験場で創作を始めるだろう。それが今後どのような創作物として世に出されるのかわからないし、内に秘められたパーソナリティはいまだに明瞭な形としてその全容をぼくたちに提示していない。きっと「Jens」が数年かけて、他者との関わりの中でその社会的なアイデンティティを形として少しずつ浮かび上がらせてきたように、「Rhoikos&Theodoros」もこれから行われていく第二、第三弾の作品展示によって (つまり他者との関わりによって)、より明瞭な輪郭を帯びていく筈だ。デイビット・ホックニーの『私の母、ヨークシャー、ブラッドフォード、1982年5月4日』のように、その姿はいくつもの要素の合成物によってぼくたちの脳内に築き上げられる。予想が立たないくらい彼らの無意識の混沌とした貯水池は深くまだ底が見えない。これからもぼくは自分なりに彼らのパーソナリティ/アイデンティティと作品の間を往来しながら、言語にして解釈を試みるつもりだ。なぜなら単調な世界に生きる飽き性のぼくにとって、彼らは白色に相当する何十もの「言葉(TEXT)」を持つイヌイットのように異なった言語体系を持つ人種で、ぼくは未だに彼らの内に広がる多彩な世界の一旦にしか触れ得ていないのだから。

参考文献
エドワード・サピア『文化人類学と言語学』弘文堂
全卓上 (2020) 『銀河の片隅で科学夜話』朝日出版社
Profile: 佐々木新 (クリエティブディレクター/物語作家)
クリエティブ・スタジオ「HITSFAMILY」にて、クリエイティブ・ディレクター、デザイナー、コピーライターとして働く傍ら、最新のアート/デザインを紹介するキュレーションサイト「HITSPAPER」や”子どもを通じて世界を捉え直す”「mewl」の編集長を務めている。また、2013年から物語を書き始めて、2016年に「わたしとあなたの物語」、2017年に「わたしたちと森の物語」を刊行。それらに併せて、言葉と視覚表現の関係性をテーマにした展示を行っている。
–